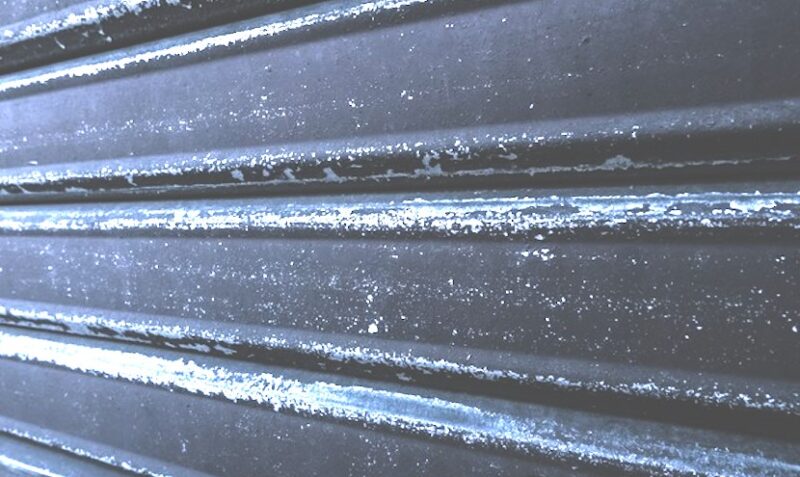父はひどくショックだったに違いない。家族に対して申し訳ないと言う気持ちでいっぱいだったに違いない。もちろん、誰も父を責めなかったし、恨むこともなかった。こんなショッキングな事件があった後も父と母はいつもと同じように毎日店を開けた。一日も休むことなく。そして何事もなかったように。それどころか、父は以前世話になっていたことのあるかまぼこ工場で、朝早くからまたアルバイトを始めた。一刻も早く日常を取り戻そうとしていた。
長い夏休みが終わった。なんとか家族総出で宿題は終わらせたものの、お世辞にもちゃんとやったとは言い難い仕上がりだった。始業式、久しぶりに会う友達も少なくない。みんな真っ黒に日焼けしている。この日のホームルームで担任の先生からクラスの女の子が転校すると発表があった。引っ越すのは同じ市内だが、校区外なので学校は転校することになったのだという。まるで僕の身代わりのようだ。彼女は明るく活発でみんなから人気があった。そして、僕は彼女と掃除の班が一緒だった。その時僕は、彼女に不思議な感情を抱いたのを覚えている。どんな感情なのかはうまく表現できないが、とにかく初めてのことで不思議な感情だった。彼女は先生に呼ばれ、大きな黒板の前に立ちみんなに向かって別れの挨拶をした。”本当は僕が今あそこに立っているはずだったのに…”いや違うか。本来なら僕と彼女があそこに立っているはずなのに、か。神様は二人同時に転校させるなんてことはしないのだろうか、などとも考えたりした。
転校も無くなったが、僕の将来の店も無くなった。でもまだコックになるという夢は諦めていない。僕はいても立ってもいられなくなり、母の夕飯の支度を手伝うことにした。最初に覚えた料理はカレイの唐揚げだった。福井はカレイがたくさん獲れる。越前ガレイや赤ガレイなどが特産品だ。それを丸ごと素揚げにする唐揚げがよく出されていた。カレイの表側というのだろうか、黒い方に包丁でばってんの切り込みを入れて、片栗粉をまぶして油で揚げる。ただそれだけのいたって簡単な料理だが油の温度に僕はこだわった。こだわったというか、それくらいしか気をつけることはなかった。ハンバーグも教わった。玉ねぎのみじん切りをする度に目が痛くなり涙が溢れる。ハンバーグを作るのにこんな苦しみと痛みを乗り越えないといけないのかと、料理人になる修行の厳しさを分かったような気になった。父から「包丁が切れないからだ」と言われ、僕は包丁を研ぐことを教わった。研ぐと行っても、砥石で研ぐのではなく、誰でも簡単に研げる家庭用の包丁研ぎでだ。
余談だが、僕の13歳の誕生日プレゼントは砥石だった。もちろん、父からである。実は、オムライスも試したことがある。全くもってうまくいかなかった。未だにぐちゃぐちゃのオムライスのままだ。小一のあの時とさほど変わらないオムライスだった。一番苦手だったのは、後片付けである。いつもやりっ放しで母が全部片付けてくれていた。父はそれを見て「後片付けまでが料理だ。出来ないなら台所へは立つな」と僕を厳しく注意した。母は「いいよ、お母さんが洗っておくから、ともひろは料理作ってていいよ」と優しかった。僕は母に甘えていたんだと気付き、洗い物も最後までやるようになった。10歳の僕は精一杯の背伸びをしていた。早く大人になって、コックになりたかった。そして、お金を貯めて、家を建てて、店も作りたかった。僕は焦っていたのだと思う。早くあの事件を忘れたかったから。
事件から数ヶ月後、僕ら家族の団地住まいは未だ変わらず、父の店「浮舟」だけが閉店した。新しい店はもう出来ないのに、それでも父は今の浮舟を閉めることにした。店を続ける気力を失ったのだろうか。それとも、事情があって閉めるしかなかったのだろうか。父のことだから、いろいろと考えた上での決断だろう。きっと前向きな決断だったのだろう。
「浮舟」は8年目を迎える前に幕を閉じた。そして父は郊外の仕出し料理屋に雇われの板前として、母はゴルフ場にキャディの見習いとして働き出した。
その時、父は41歳、母は35歳だった。
つづく