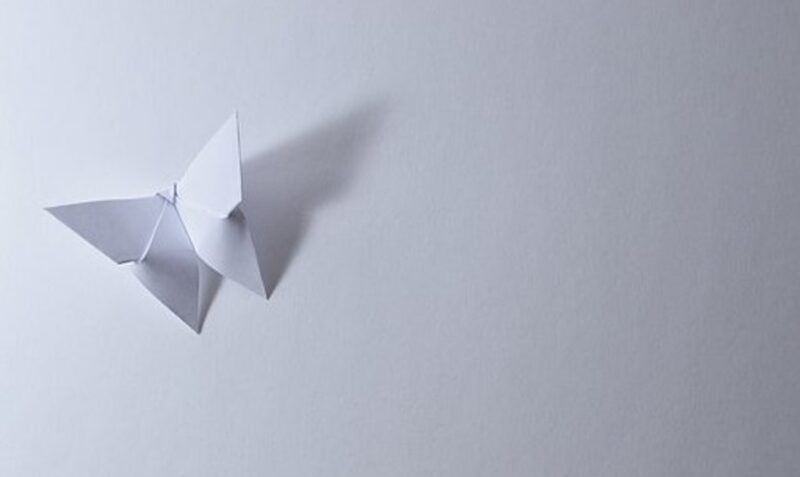僕がフランス料理の道を選んだのは、運命だったように思う。フランス料理という、一見すると華やかな言葉の響きとは裏腹に、その道はひどく険しく辛いことだらけだ。フランス料理の世界に限らず、どの料理の世界でも、いや、どの分野であっても何かを極めようとその道を歩き始めたならば、怒涛の如く立ちはだかるいくつもの壁に苦しむことを覚悟しなければならない。”いくつもの壁”それは神の手により、自分の成長とともに、それを超えてさらに高く積み上げられるのだから、己の脚力だけでは飛び越えられないこともある。時には両手の指を壁に食い込ませ、歯を食いしばるが、それでも重力に逆らえない時もある。ある時、父の叶えられなかった密かな夢を、僕は覗いてしまった。それは古ぼけたダンボールの中にずっしりと佇んでいた。それからというもの、僕の心に、父の、その夢が住み着き、僕はこうしてフランス料理を作っている。
僕の父は昭和18年に福井県の大野で生まれた。大野には立派なお城があり、その昔は城下町として栄えた。雲海に浮かぶように見える幻想的なそのお城は天空の城と言わしめるほどに、今なお美しい。父が生まれたときにはすでに祖父はおらず、祖母が女手一つで父を育てた。戦時中と言うこともあり、父親がいない子供は珍しくなかった。父は中学を卒業すると芸者である祖母の伝手て金沢の料亭に丁稚奉公に行く。当時15歳だった父は、料理人になりたかったわけではないが 、それしか生きる道はなかった。自分で自分の道を選べる年齢でも、時代でもなかったからだ。日本テレビが世界ではじめてプロ野球をカラーでナイター中継し、IOC総会が第18回オリンピックの開催地を東京に決めた年だった。そして十数年後、父は福井に戻り母とお見合い結婚をした。お見合いで初めて出会ってからたった3回で結婚式を迎えたと母から聞いたことがある。当時のお見合いとはそう言うものだったらしい。
僕が生まれたのは昭和48年。第二次ベビーブームの真っ只中に生まれ、その年の秋には第一次オイルショックが起こった。福井市内にある長屋のような2階建ての団地に二つ下の弟と祖母との5人家族で住んでいた。部屋が2つしかない狭い団地だったが小さな庭もあり、そこに松の木が1本植えてあったことを今でも覚えている。
僕が物心つく頃、父と母は二人でカウンターだけの小さな料理屋を始めた。毎朝、二人は僕を幼稚園に送りとどけてからお店の準備を始める。弟はまだ小さかったため祖母に預けていた。お店は福井市内に新しく出来たアーケード街の一角にあり、僕は幼児園が終わると幼稚園のバスで毎日お店に行く。そして、当然のごとく閉店まで両親と一緒に過ごした。父がお店の厨房の隅に囲いを作ってくれ、畳が一枚敷かれたその中で僕は3歳から6歳までを過ごした。
遊びといったら、皿洗いをしたり玉葱の皮をむいたりといった手伝い(のようなもの)が主だったが、3歳の子供が役に立ったとは到底思えない。途中で飽きてしまうこともしょっちゅうあったし、そもそもお皿がちゃんと洗えていたのかも怪しいものだ。おそらく、母があとで全部洗いなおしていたのだろう。玉ねぎの皮むきについては、玉ねぎの上の方を父が少し切り落としてくれ、それを刃先が丸くなって切れなくなったペティナイフで僕が皮を剥く。刃の部分はガムテープで巻いて切れないようになっている。ナイフで剥くというよりむしる感じ。子供には難しそうだが毎日やっていればなんとかなるものだ。役に立たなくても、邪魔であっても、そうして遊ばせておいて子育てをやり過ごすしかなかったのだろう。
父は狭い厨房で、手際よく、無駄のない動きで料理を仕上げていく。そんな、厨房で料理を作る父の背中を見て僕は育った。特に、僕にオムライスを作ってくれるときのそのリズミカルなフライパンさばきは見ていて楽しかった。右手でフライパンの柄をトントンと叩くごとにフライパンの向こう側においた赤いケチャップライスが、薄く焼けた卵にくるくる巻かれ、あれよあれよという間に黄色いオムライスになる。まるで魔法のようだ。幼稚園でもオムライスを食べたことのある子はたくさんいたけれど、このオムライスの魔法は僕しか知らない。
お店を閉めるのはいつも夜の10時を回っていた。シャッターを閉めたら大きなゴミ袋を2つ持ってお店の裏にあるゴミ捨て場に捨て、それから車で家に帰る。家までは15分程度だったが、その間に僕は寝てしまう。寝てる子供を抱っこして車から布団まで運ぶのはひと苦労だったらしい。そりぁそうだろうな、と思う。
父の左足は事故の後遺症が残っていて、歩くと左足を少しひきずっていた。まだ見習いの頃、スクーターに乗って出前に行く途中でその事故は起こった。トラックが父のスクーターに気づかず左折して巻き込まれたのだ。すぐに救急車で運ばれ命に別状はなかったものの左足はしばらく動かなかった。すぐに手術をすれば完全に治るはずの怪我だったが、見習いが仕事を休むわけにもいかなかったし、3万円という手術費も当時は払えなかったと祖母が嘆いていたのを聞いたことがある。足の悪い父にとって長時間の立ち仕事はとても辛かったが、そんな事は物ともせず、父はがむしゃらに修行に励んだ。
母は福井県の鯖江と言うメガネ産業で発展した街で生まれたが、幼い頃に両親を病気で失い親戚に引き取られて育った。中学を卒業すると繊維工場で働くことになる。本当は服を作る縫製の仕事に就きたかったが当時は好きな仕事を選べる状況ではなかったのだ。工場の仕事も親戚の口添えで入った。いつか服を作る仕事をしたいと言うのが母の夢で、一生懸命働いて貯めたお金で電気ミシンを買った。父と結婚した時の嫁入り道具はその電気ミシン一台だけだったらしい。ただ、父と料理屋を始めることになり母はその夢を諦めた。だから電気ミシンは母にとって残された夢のかけらのようなものなのだ。嫁入り後もずっと大事に大事にしていた。そして、その電気ミシンで僕ら兄弟の服をよく縫ってくれた。
こんなエピソードがある。僕が高校生の時、当時流行っていたダブダブの学生ズボンを母はかっこ悪いと言ってスリムな細めのズボンに縫い直したことがあった。僕はそれこそかっこ悪いと母と大喧嘩したが、そのズボンの仕上がりは素晴らしく、まるで初めからそんな形のズボンだったかのようだった。足首のあたりはかなり細くなっていてファスナーが縫い付けられ、ファスナーを開けないと足首が入らないほどの細さだった。かなり斬新なデザインに思えたが、履いてみると意外にもしっくりときてシルエットも美しく、結局僕はそのズボンを気に入った。クラスでも評判になり、その時ばかりは母を誇らしく思ったことがある。ただし、そのズボンは校則違反とされ先生にこっぴどく叱られた。
実は父にお店を出そうと言い出したのは母の方からだった。結婚後、福井で板前として働いていた父は、その強い料理へのこだわりやプライドが邪魔をしてかお店を転々としていた。そんな父を見兼ねた母は、「自分でお店出したら?私が手伝うから」「お父さんは腕がいいさかい絶対繁盛するって」と、父の背中を押したのだった。母は、自分の夢などたかが知れてると思った。辛い修行を乗り越えて手に職をつけた父こそ、その腕を発揮できる場所が必要だと思った。そしてそれが家族の幸せになると信じた。親もいない、身寄りもほとんどない自分を嫁にもらってくれ二人の子宝にも恵まれたのだからもうこれ以上望むのは贅沢なこと。この電気ミシンがあればいつでも服は縫えるし、彼ほどの料理の腕ならばきっとお店も繁盛する。母は静かにそう思った。
そんな母の覚悟に父は頷き、借金をして店を持つことになる。店は「浮舟(うきぶね)」と名付つけた。
つづく